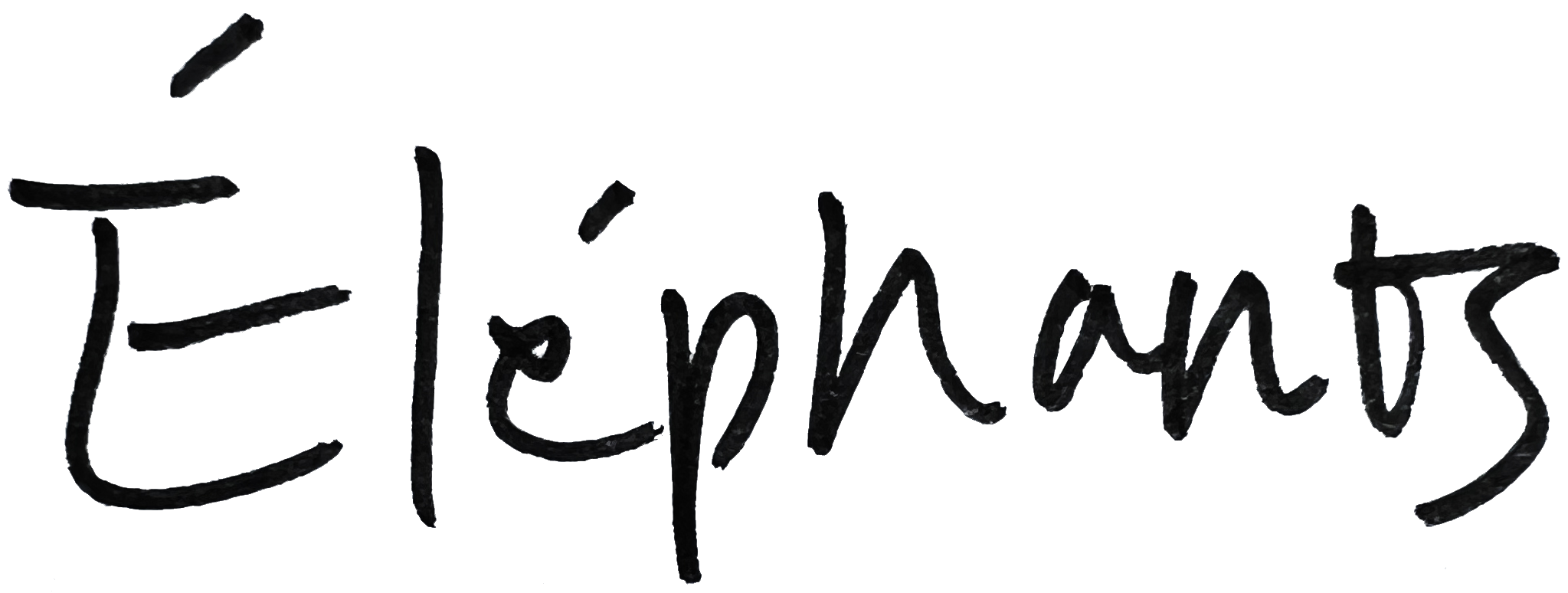2025.09.24
#10 日々を豊かにする 一期一会のヴィンテージたち
日本でも人気が高く、馴染みの深い北欧の雑貨たち。曲線が美しいガラス製品やテーブルウェア、個性的な絵柄のファブリック、温もりある木製品。現地の美しい自然環境と、厳しい気候から生まれたデザインは、合理的で凛とした佇まいの中にどこか懐かしさや親しみを感じます。インテリアショップや百貨店には有名デザイナーの作品が並び、実際に見たり手に取る時にはなんだか少し特別感がありますが、その実用的でミニマルなデザインはどれも、現地の暮らしの中で必要とされ生みだされたもの。冬が長く家の中で過ごすことの多い北欧で愛される、暮らしをよりよくするためのデザインの数々。長い歴史の中で人々に愛され、生活を豊かにしてきた製品は、ヴィンテージ品として今も大切に受け継がれています。時を超え、海を越えて、ここ、日本でも。
新静岡駅のバスターミナルから程近く、落ち着いた裏通りのビルの2階に雑貨店の cotory(ことり)はあります。白を基調とした店内には、オーナーの清水さんがフィンランドで買い付けた北欧のヴィンテージ雑貨とこだわりのセレクトアイテムが、柔らかい自然光に包まれ並んでいます。

Photo by Sayuri Shimizu (cotory)

Photo by Sayuri Shimizu (cotory)
アトリエペネロープとは創業初期の頃からのお付き合いで、最近は別注のコラボアイテムを製作したり、定期的にウェアのイベントも開催いただいています。以前店舗を構えていた藤枝から2018年に現在の伝馬町へ移転。内見の時に窓から借景の美しい桜の木が見えたことが決め手となり物件を決められたのだそうです。
長年 cotory を運営されてきた清水さんから「今後は買い付けたアイテムを静岡以外でも販売し、もっと多くの方に見ていただきたいと考えている」というお話をお聞きしたのが今年の春先のこと。そこで「ぜひ第一回目をペネロープで」と提案させていただき、今回「cotory Vintage Market at ateliers PENELOPE」の開催が実現しました。いつもの中目黒ショップ店頭に、バッグやウェアと共に北欧ヴィンテージ雑貨が並ぶ、私たちにとっても初の試みとなるイベントです。
残暑厳しい9月初旬、Bonjour biqui Bonjourの白いコットンワンピースを涼しげに纏い、いつもと変わらぬ朗らかな笑顔で訪ねてきてくれた清水さん。一足早くお送りいただいていた今回出展するアイテムと共に、イベントに先駆けて色々とお話を伺うことができました。
-「cotory」をはじめたきっかけについて
「聞かれるたび困っちゃうんですけど…たいした理由はないんですよ。」と、くすりと笑いながら話しはじめた清水さん。
元々海外に行くことが好きだったという清水さん。社会人になって少し経った頃、これから先のことを思った時に、このままお勤めしているより何か自分でやってみたいなという気持ちが芽生えたのだそう。雑貨屋に強い憧れがあったわけではなかったけれど、『自分も現地に行けて、好きなものを仕入れてくる、そんな自分の好きなことなら続けられるのでは』と、半ば思いつきのように始めた雑貨店。
「地元の静岡ではバイヤーとして雇っていただける仕事なんてまずなかったので。それなら自分でやっちゃおうと。いきなりお店を借りてまずは形から始めちゃったんです。正しいやり方もよくわからなかったけど、自分でできる範囲でやってしまえばいいかなと。」
そう笑顔で話す清水さんのおおらかな語り口調からは、森の中の木々のようにのびやかでたくましい芯の強さを感じます。流れに無理やり逆らうのではなく、自身がワクワク、そして心地よいと思える風向きを確かめながら、歩みを進めて自然に辿り着いた先が今のお仕事だったんですね。
お店を始めた当時は今ほどインターネットも普及しておらず、宣伝手段は地元の新聞の折込チラシと情報誌。最初は集客に苦労し、オープン前に手始めに買い付けてきた商品も今のような品数や厚みはなかった。それでも、「珍しいですね」と手に取り買ってくださるお客さまに支えられ、続けようと思えたのだそう。清水さんが cotory と共に着実に歩み続けたこの20数年の間に、フィンランドが舞台の映画がヒットしたり、今はすっかり定着した北欧のブランドが続々と日本進出するなどし、北欧デザインは私たちにとって一層身近なものとなりました。

来年25周年を迎える cotory 。北欧輸入雑貨店の先駆けともいえる清水さんの目線でセレクトされた一線の拘りが感じられるアイテムたちは、変わらず北欧雑貨好きのファンの心をくすぐり人気を集め続けています。
ヴィンテージ、いわゆる古道具はどれも1点ものばかり。同じデザインがあったとしても、そのコンディションは様々で製作年によっても異なります。cotory で扱うアイテムは、セレクトと現地での買い付けはもちろん、商品の撮影もすべて清水さんが行っています。1点もののため、どなたかの手に引き取られれば売り切れとなってしまいますが、cotory のオンラインショップではそれらのアーカイブもご覧いただくことができます。
-店名「cotory(ことり)」の由来は?
「まず横文字の店名を覚えるのが苦手で(笑)日本語の名前がいいなと思って響きで決めました。色々書いたり口に出してみたりして。今ではちょっと可愛すぎちゃったかなとも思うんですけど、小さい鳥の「小鳥」ではなく、「ことり」という何か物を置くときの音のイメージで決めました。」
ガラスや陶器でできたヴィンテージのテーブルウェアを並べていると少し低めの「ことり」という音が聞こえてきます。そのまま綴ると「cotori」ですがイギリス人の友人にお店を開くことを話した時、書いてもらった綴りが「cotory」。それをそのまま店名にしたのだそうです。
北欧雑貨店 cotory の原点は意外にもイギリスにありました。イギリスのアンティークに魅せられて、昔はよく格安の北欧の航空会社の乗り継ぎ航空券を買って渡英をしていたという清水さん。せっかくなので旅程を延ばし、乗り継ぎ地のフィンランドにも立ち寄ってみたところ、「いいところだな」と不思議な心地のよさを感じたのだそうです。そうして、たびたびフィンランドを訪れるようになり、知人から現地に住んでいる日本人を紹介されて会いに行ったり、だんだんと縁がつながり知り合いも増えていったのです。もし乗り継ぎが他の国だったら、cotoryは違う趣のお店になっていた可能性もあるのでしょうか。お店を始めた時のお話と同様に、とても清水さんらしいエピソードだと感じました。
「北欧のプロダクトはありそうでない絶妙なデザインのものが多くて、日本の生活に取り入れやすく相性のよいものが多いように感じます。よくフィンランド人は日本人に似ていると言われることもあるみたいですが、やはりそれも関係あるのでしょうか?」
そう話すのは、フィンランドのことわざ『内向的なフィンランド人は自分の靴を見ながら他人と話す。社交的なフィンランド人は相手の靴を見ながら話す。』を最近知ったというスタッフ。シャイ気味な人の一面を自虐的かつユーモアたっぷりに例えたことわざですね。
「なんとなくわかる気がします(笑)」と笑う清水さん。
「今回出展するティーポットもそうなんですけど、日本のデザインを参考にして作られたデザインはけっこう色々あるので。やっぱりそういう通ずるものってあるのでしょうね。」
とはいえ、性格はもちろん人それぞれで、シャイなフィンランド人もいれば、とても気さくな方も沢山いらっしゃるのだと、現地での体験談を交えながらお話ししてくださいました。
「特に買い付けの合間は明らかに現地人ではない自分に話しかけてくれる方が本当に多くて、古い道具が好きな人たちにはそういう方が多いのかもしれません。」

-清水さんのセレクトのこだわりについて
「基本自分の好きなものですが、日本の生活に取り入れやすいもの、かわいすぎないもの、というのは気をつけて意識しています。」
一口に「北欧」と言ってもそのバリエーションは多岐に渡り、甘く可愛らしいデザインのものも数多くありますが、清水さんはそれを求めず、あえて選ばないようにしているそうです。現地を旅しながら骨董市やアンティークショップで買い付けるヴィンテージ品との出会いはまさに一期一会。今回イベント用にセレクトしていただいたアイテムからも、分かりやすいポップさや人気があるかどうかより、清水さんが長年磨かれてきた感性と、心の琴線に触れる何かがあるかどうかを指針にされているのだろうということが伝わってきます。
思わぬ場所・予期せぬタイミングで、心の中にぼんやりと留めていた『なんだか、いいな』に偶然出会えることが時々あります。予め何かを求め期待を持ってお店や旅先に足を運んだ時よりも、前者の出会いがもたらしてくれる感動にも似た幸せな感覚は、何事にも代え難く確実に人生の中で意味を持ちます。今回のヴィンテージ展もお客様にとって一期一会を楽しんでいただける素敵な出会いの場になればと願っています。

-現地での買い付けについて
今年6月、いつもより少し長めの3週間、フィンランドへ買い付けの旅へ出かけられていたという清水さん。行く街はおおまかに決まっていて、骨董市のタイミングも測って今回は3箇所の拠点を回り買い付けを行ったそう。
「夏の短いフィンランドは一年で一番日が長くなる夏至の時季がベストシーズンなのでおすすめです。フィンランドの骨董市は本当にどこも賑わっていて楽しみにしている人が沢山いらっしゃる。現地では娯楽が少ないので、アンティークショップ巡りや、骨董市が人々にとってレジャーなのかもしれないです。ひとつの骨董市に行くと、『来週のも来るでしょ?!』なんて誘われることもあります。」
ときどき cotory の Instagram でも拝見させていただいている、清水さんが現地で撮影された写真がとても好きで、今回何枚かお借りしましたのでこちらでご紹介させていただきます。初夏の新緑に包まれ、屋外の骨董市に集った人々の様子がとても気持ちよさそうです。

Photo by Sayuri Shimizu (cotory)

Photo by Sayuri Shimizu (cotory)

Photo by Sayuri Shimizu (cotory)
フィンランドと聞くとなんとなく森や湖のイメージが強かったのですが、清水さんのおすすめは『島』。ヘルシンキは海に面した都市。バルト海は島が多く、内海なので基本的に波も穏やか。フィンランドの地図を拡大してみると、ヘルシンキ周辺には無数の小さな島々が点在しています。バスのようにフェリーが通っており、数時間もあれば気軽にショートトリップすることが可能で、周辺の島には昔の建築が残っていたり、ミュージアムや地ビールレストランがあったり、散策を兼ねた観光にとてもおすすめだそうです。
「それこそ休日には、松の木のかごにサンドウィッチやワインの瓶を入れて、それを持ってフェリーに乗り、島へピクニックに出かける人もいたりして。」
なんて最高な休日の過ごし方でしょう。清水さんもいつも旅の終わりに時間ができたら島へ渡り、旅を振り返りながらビールで一息つくことを楽しみにしているそうです。スタッフもフィンランドに行った際にはぜひ真似してみたいと思います。
-今回出展するアイテムのご紹介
イベント用にセレクトいただいたアイテムから、清水さんのおすすめ、そしてスタッフが気になったアイテムをいくつかピックアップしご紹介します。


ARABIA PRISMA グラス(1970年代後半)
リズムのように光の反射と屈折が楽しめる、Kaj Franck(カイ・フランク)のデザインのガラスシリーズ。表面の角度の切り替えを表側と内側でずらしただけで出来るボーダーは、持ちやすく溢れにくいよう緻密に計算されています。数種の大きさで作られましたが、この大きさが最も使いやすいサイズ。
しっかりとした厚みとほどよい重み。手にぴったりと吸い付くようなサイズの日常使いしやすいグラスは、3層の帯のように異なる傾斜でカットされた側面の絶妙な段差が、グラスの中に光を取り込み名前の通りプリズムのように上品に輝きます。
「一見なんてことないデザインに見えるけどすごく良く考えられているなと思って。昔からすごく好きなデザインです。色のついたガラスも好きだけど、これは透明なのでワインを飲むのにもおすすめです。ビストロで飲んでるみたいに。」



FISKERS TRIENNALE ナイフ・フォーク(1957年〜)
金工の巨匠として国際的評価も高いBertel Gardberg(ベルテル・ガードバーグ)が1957 年にデザインを手がけました。黒い樹脂の持ち手は食卓を引き締めます。裏面にFISKERS のロゴと FINLAND の刻印があります。
「ローズウッドやチークなど柄が木で作られたレアなものもあるのですが、これはポリアミド樹脂で普段のお手入れも楽。木目がはいったような黒い柄は食卓が締まる感じがしてすごく好きなんです。」
角ばったマットな黒い柄と、程よい丸みのステンレスのコントラストが、接合部で溶け合うように一体化した美しいデザイン。サイズも大きすぎず、和洋どちらのシーンでも日常使いがしやすそうで、手に持った時も軽やかです。
「実は北欧ヴィンテージの入り口としてカトラリーがすごくおすすめなんです」
(意外で一同「えーっ」と驚き)
「というのは、ステンレスは欠けたり割れたりしないので。惜しみなく使えますし、なんなら一生使えるかも。最初に買っていただくとしたら私は入門編としてカトラリーをおすすめします。」
どちらのアイテムも、言われてみないと一見ではその奥深さに気づくことができませんでした。派手さはないけれど、そのシンプルさの中にある機能美、そして計算された「ちょっと他とは違う何か」を秘めたデザインは、実際に使う人が手にして初めて完成するのだと思います。なんというか、すごく清水さんらしさが凝縮されたセレクトだと思いました。
続いて、スタッフYがセレクトしたのは2つの置き物たち。


HUMPPILA 社 ガラスのハリネズミ(1970 年代)
1970年代にガラス製品の製造をしていたHUMPPILA社のガラスのハリネズミです。HUMPPILA 社は ARABIA や iittala と同じく WÄRTSILÄ 社の傘下に入り現在ではガラスの製造は行なっていません。庭や公園に現れる愛嬌溢れるハリネズミはフィンランドの人々にも愛されています。デザイナーは分かりませんがコロンと丸いフォルムがとても可愛らしいペーパーウェイトです。ブランドラベル有りダメージのない大変良好なコンディションです。
フィンランドではとても身近な動物だというハリネズミ。ガラス製のどっしりとしながらも愛らしい、手のひらに収まる丸いフォルムは、その体の中心に集まった柔らかな光を放つ様がとても美しい。
「やっぱり冬が長い国なので、こういうガラスの置物を窓辺に置いて、部屋の中に光を呼び込むというのは多い気がします。」
前述の通り清水さんもあまり可愛らしいものを選ぶタイプではないそうですが、元々ぬいぐるみなどの可愛らしいものはあまり好みではないというスタッフも、こちらの置き物にはどこか心をくすぐられたと言います。
一見無機質なガラスに投影されたハリネズミの姿から、臆病でマイペース、でもどこか愛嬌のある性格が柔らかい光の中に透けて見えるようで、その媚びのない愛らしさはずっと傍に置いておきたくなる、そんなアイテムです。

陶器のツバメ(年代不明)
羽を休める陶器のツバメ。喉元が赤くないので、日本では見かけないニシイワツバメでしょうか。すっきりと簡素化されたフォルムがとても格好良くそしてとても可愛らしいです。ダメージのない大変良好なコンディションです。
とてもシンプルなフォルムとカラーリングですが、一目でツバメだと認識することができます。ツバメはフィンランドの夏の訪れの象徴。現地では古くから「鳥が幸せを運んでくる」という言い伝えがあるのだそうです。そういえば、鳥がモチーフの雑貨やファブリックを目にすることがとても多い気がしますし、実際にこういった陶やガラスのオブジェが多数作られ、人々に愛されてきたようです。
今回のイベントではこちらの一羽だけ中目黒に遊びに来てくれていますが、静岡の cotory のショップではヴィンテージ展と同じく、10月13日(月祝)まで「SUOMEN LINNUT フィンランドの鳥たち」と題したフィンランドのヴィンテージの鳥の置き物たちだけを集めた展示イベントが開催されております。その数なんと50羽ほど。またとない機会ですので、気になられた方はぜひ足をお運びください。
SUOMEN LINNUT フィンランドの鳥たち
10月13日(月祝)まで cotory にて開催中
《詳細はこちらをご覧ください》
この投稿をInstagramで見る
-最後に、北欧のヴィンテージアイテムを日々の生活に取り入れることについて、清水さんからのメッセージ
「全部を全部、ヴィンテージに揃える必要はなくて。意外と、自分もすべて北欧で揃えているかというとそうではないので。民藝のものを取り入れたりしていますし。最初のほうにお話しした通り、北欧のものは日本の生活に取り入れやすいものが多いと思うんですね。まずは何か一つ、取り入れてみるのがいいと思います。やっぱり気に入ったものって、今まで集めてきた自分の持っているお気に入りとも自然とマッチすると思います。かけ離れたものは選ばないはず。」
今回のお話を伺う中で、昔は現地に山のようにあった品が最近は数が少なくなり、買い付けも難しくなっているという事をお聞きしました。自分のために買った食器や、それこそ壊れないカトラリーは、お値段に関わらず一度買うとなかなか買い替えられるものではないなと私も最近実感しているのですが、だからこそ慎重に、本当に気に入ったものを選んでいきたいなという思いがあります。少しお値段が張っても、毎日の生活にお気に入りを取り入れることで、それは『物』である以上の彩りと豊かさを日々与えてくれるのではないかと思います。
「本当に私も、そんなに数は持ってないので」とおっしゃる清水さんは、物によって使う頻度の差はあれど、やはり基本は使うものだけを手元に置いているそうです。大切に扱いたいと思うからこそ、大切にしすぎて実用性が伴わない、というのはよくある話で、みなさんも同じような経験があるのではないでしょうか。
「道具はやはり使ってなんぼ。わりと丈夫なものも多いですし、眺めるだけ、使わないものより、『使えるもの』を選びます。もし割れてしまっても、それはまた、新しいものが買える(出会える)と思えるので。」
大切に使い続けること=固執することではなく、何かひとつを手放すことでその時の自分に相応しい、新たな出会いがまた訪れる。これはヴィンテージを日常に取り入れることにおいてだけではなく、私たちの生活のすべてに通ずる大切なマインドのような気がします。そしてそれはフィンランドのデザイン理念(デザインはよりよい日常のために)にも適っているのではないでしょうか。

今回、清水さんからお話を伺って、今まで知らなかったヴィンテージ雑貨の世界、そしてフィンランドの魅力の奥深さに触れることができました。そして改めて、日常の中でふと訪れるささやかな一期一会にアンテナを張り、大切にしていきたいと感じました。
清水さん、貴重なお話を有難うございました。
Kiitos(キートス)!!
「cotory Vintage Market at ateliers PENELOPE」は10月1日(水)〜13日(月祝)までの開催です。期間中、最終の12日(日)、13日(月祝)の2日間は、通常は定休日ですが特別営業いたします。期間中、情報は ateliers PENELOPE の Instagram でも発信していきますので、合わせてご覧ください。
みなさまのお越しをお待ちしております。

cotory Vintage Market at ateliers PENELOPE
2025年10月1日(水)-10月13日(月・祝)
ateliers PENELOPE
ADDRESS 東京都目黒区東山2-10-8-2F
TEL 03-5724-3815
OPEN 11:00-19:00
*日・月曜定休
*10月12日(日)、13日(月祝)は特別営業いたします。

cotory(ことり)
OFFCIAL WEBSITE
ONLINE STORE
Instagram @cotory
写真・動画・文 / Nao Watanabe
©️2025 ateliers PENELOPE